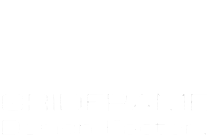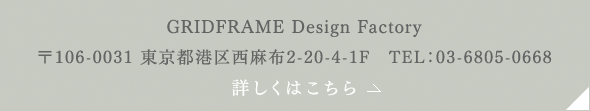「そこにしかないお店」をつくる
「このところ、巷では何年も『よく見かけるようなお店』がつくられ続けていますよね。」
・・・と語る商業空間雑誌の編集者さんはその理由を次のように分析する。
「カタログから手に入るものが充実したからじゃないかと思うんです。デザイナーのつくりたいものがカタログから手に入ってしまうんですよ。」
以前は、デザイナーは自分がつくりたいものは、一からつくるしかなかった。でも、だからこそ、「そこにしかないお店」がたくさんつくられたのだ、と。
そうか、カタログから手に入るものはそんなに充実しているのか・・・、などと感心しているぼくたちは、当然のように、自分がつくりたいものは、一からつくり続けている。
ぼくたちには、工場がある。カタログで選ぶよりも、つくった方が早いものがたくさんあるのだから、「そこにしかないお店」しかつくれない。
逆にいえば、ぼくたちは、「そこにしかないお店」をつくりたい人のための会社だ。
現在、開業から5周年を迎えられるお店は全体の2割に過ぎない、といわれている。
カタログから手に入るものの充実と情報社会のおかげで、巷では「よく見かけるようなお店」を安くつくることができるようになった。
それに合わせて、一般的なお店づくりのコストの基準は押し下げられ、銀行からの一店舗当りの開業時融資額も引き下げられていった。
ある意味、「よく見かけるようなお店」をつくることを社会が推奨しているかのように。
だが、永く続くお店のほとんどは「そこにしかないお店」であることに、社会は気づいていない。
このままでは、5周年を迎えるお店の割合を増やすことはできないだろう。
では、「そこにしかないお店」と「よく見かけるようなお店」の違いはどこにあるのか。
例えば、カスタマーの側に立って、カウンターにどんな材料が使われているか、を見る。例えば、同じ合板でも、なんらかの手をかけて仕上げされた合板の場合と、カタログから選んだメラミン合板そのままの場合でどのように感じ方が違うだろうか。
前者からはお店を営む「人」が感じられ、後者からはそれが感じられないのではないだろうか。
「そこにしかないお店」のそこにしかないものには、オーナーのお店に対する潔い「覚悟」が表れるのだ。
一方、「よく見かけるようなお店」のカタログから選ばれた材料からは、それが感じられない。空間からは、オーナーが人生を賭けている感じがしない。
ぼくたちは、素材として鉄をよく使うけれど、鉄でつくることによって、オーナーがその店にどっしり錨を下ろした感じが、知らず知らずのうちに表れているのだと思う。
カスタマーから見れば、そのような店がすぐになくなるとは決して思わない。だから、カスタマーは安心してリピート客になれるだろう。
この分野に限らず、一からつくるものが持つ力を社会が再認識することで、現在では稀少になった腕のよいつくり手もまた増えるに違いない。
ぼくたちグリッドフレームの活動が、未来を創造するために必要不可欠なものづくりの力を増強することにつながれば、と願っています。